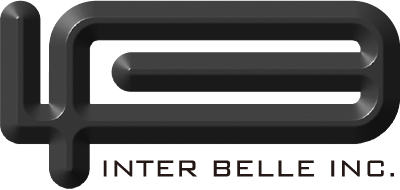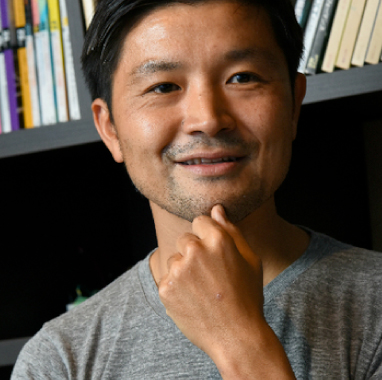- インター・ベルTOP
- アパレル・ファッション業界の求人・転職 SOW.TOKYO
- THINK
- ANOTHER STORY
- 欧テクノロジーアートの今
“モノづくり“という共通のフィールドで活躍する異業種クリエイターのインタビュー
欧テクノロジーアートの今ダヴィッド・ルテリエ /モーリッツ=サイモン・ガイスト

PROFILE
ダヴィッド・ルテリエ /モーリッツ=サイモン・ガイスト
【David Letellier ダヴィッド・ルテリエ】
独ベルリン在住アーティスト/音楽プロデューサー。建築、アート、音楽にまたがるアプローチで、オーディオビジュアル・パフォーマンスからサウンド・インスタレーションまで、さまざまな媒体で表現を行う。
【Moritz Simon Geist モーリッツ=サイモン・ガイスト】
独ドレスデン在住コンテンポラリー・アーティスト。『Sonic Robots』として、エレクトロニック・ミュージックのパフォーマンスや、ロボティック・サウンドインスタレーションなどさまざまなプロジェクトを展開。これまでにアルス・エレクトロニカや、Transmediale等で作品を発表している。
人と機械との間の“主従関係”を問う作品「Versus(ヴァーサス)」
2011年に発表したこの「ヴァーサス」は、向かい合う2つのマシンが応えあうというもので、それぞれのマシンの動きを通じて、空間の概念を音と結びつけて表現しています。それぞれが搭載したアルゴリズムに沿って独自で音を発し、片方のマシンがその音に反応して動きに変換するという仕組みです。
この作品は観客が何かアクションをして、マシンがそれに応えるというような、よくある人と作品との間のインタラクションではありません。2つのマシンのダイアログを見せるもので、観客はむしろマシン同士の関係性を干渉しているただの“要素”でしかない。あえてそういう表現から一線を画したかったのです。
人間=主、マシン=従、という、ある意味人間を中心とした考え方を逆にして、人とマシン(AI)との関係性を見た人に考えさせるのが目的です。
一方で、音と空間の関係性を、作品の動きを通して音を可視化してみせるという目的も持たせています。
マシンが吸収(録音)した音が動きとして表現され、その動きがまた音に変換される…というループで拡散されていく、そんなイメージの作品です。
人の感情に働きかけて、揺さぶるクリエイションを追求
今回の作品では、アルゴリズムを取り入れて、応えあう2つのマシンを完成させましたが、私はテクノロジーにこだわっているわけではないんです。常にコンセプトありきで、この「ヴァーサス」ではたまたまこのような表現にたどり着いただけ。アルゴリズムを搭載することになり、急きょプログラミングの知識が必要となったので、勉強はしましたね。
テクノロジーはあくまでも表現方法の一つであって、あるテクノロジーにのめり込みすぎると、それにばかり捉われてしまって、最初のコンセプトを見失ってしまうのではないかと思っています。
私は作品を通して観客の感情を揺さぶりたいと考えていて、マシンやテクノロジーそのものよりも、それらが生み出すことのできる可能性に興味があるんです。それが観客にどう影響を及ぼすのか、とても興味深いです。
私は今ミュージシャンとしても仕事をしていて、毎週末、世界各地で活動しています。アイデアはすごくたくさんあるんですが、それをカタチにする時間がほとんど取れなくて…。でもゆっくりですが、また新たな作品を作り続けていきたいと思います。

リサーチ10年を経て完成したロボティック・サウンド
今回展示した作品「Tripods One」は、5つの音響ロボットが、それぞれエレクトロミュージックを演奏するというもの。各ロボットはネットワーク等の連携はしていません。独自に音を作り出すようになっているのですが、メインのコンピューターでエンジニアが操作し、コントロールしています。5年前にはドラムマシンを観客がインターフェイスで操作して音を出すというインタラクティブな作品を発表しましたが、今回は私自身がロボットをコントロールしたいと思ったのです。
この仕組みづくりのためのリサーチに10年の歳月を要しました。各ロボットが発するそれぞれの音に加え、光もアルゴリズムでシンクロさせていますが、とても難しかった。そのあたりは技術の精度に関わってきます。音として心地良いものを生み出すために、研究を重ねた結果がこの「Tripods One」となりました。
「Tripods One」は非常に未来的な作品です。見る人にアグレッシブさ、尖った印象を与えるものだと自分自身は思っています。
ロボットとかコンピューターというと、完璧さをイメージする方もいると思いますが、リサーチを重ねていくうちに分かったことは、ロボットもエラーを起こすということなんです。その点にとても人間らしさを感じて、この作品のクリエイションのプロセスに取り入れています。
※インスタレーション「Tripods One」はゲーテ∙インスティトゥート /東京ドイツ文化センターにて2017年2/21~2/26まで展示されました

進化し続けるロボット×AIで新たなクリエイティブを模索
今はまだ、ミュージシャンとして表現したい音楽に技術が追い付いていないのが現状ですが、来年あたりにはカタチにしたいと思っている作品があります。
それはTripods Oneとも似ていますが、作曲するロボットやリズムを刻むロボットなどを5つ配して、それぞれが一ミュージシャンとして独立して動きつつもお互いが会話をするように光でコミュニケーションを取りながらアンビエント・ミュージックを生成するというものです。
ロボットと人工知能は異なる発展をしていますが、変化が激しいのは人工知能の方ですね。ただ、今の人工知能は単なるアルゴリズムに過ぎないので、クリエイティビティとはまだ距離がある。でも数年後にはロボットと進化した人工知能を組み合わせてもっと面白いものが出来るのではないかと期待しています。
スマートフォンに話しかけると音声認識して応えてくれるように、今や人工知能は何も特別なものではなくてそこにあるもの。でも具体的にどんな仕組みになっているのか一般の人にはわからない。そんな感じでどんどん進化していくのだと思います。人工知能の進化は2045年のシンギュラリティで人間を超えるとも言われていますが、あくまでもそこは人間がコントロールしていくべきだと思いますね。

進化し続けるロボット×AIで新たなクリエイティブを模索
今はまだ、ミュージシャンとして表現したい音楽に技術が追い付いていないのが現状ですが、来年あたりにはカタチにしたいと思っている作品があります。
それはTripods Oneとも似ていますが、作曲するロボットやリズムを刻むロボットなどを5つ配して、それぞれが一ミュージシャンとして独立して動きつつもお互いが会話をするように光でコミュニケーションを取りながらアンビエント・ミュージックを生成するというものです。
ロボットと人工知能は異なる発展をしていますが、変化が激しいのは人工知能の方ですね。ただ、今の人工知能は単なるアルゴリズムに過ぎないので、クリエイティビティとはまだ距離がある。でも数年後にはロボットと進化した人工知能を組み合わせてもっと面白いものが出来るのではないかと期待しています。
スマートフォンに話しかけると音声認識して応えてくれるように、今や人工知能は何も特別なものではなくてそこにあるもの。でも具体的にどんな仕組みになっているのか一般の人にはわからない。そんな感じでどんどん進化していくのだと思います。人工知能の進化は2045年のシンギュラリティで人間を超えるとも言われていますが、あくまでもそこは人間がコントロールしていくべきだと思いますね。